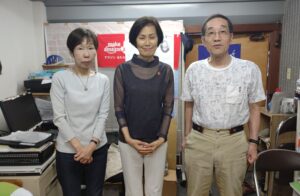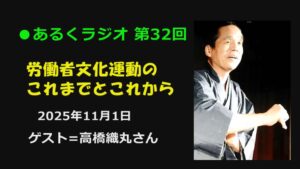●笠啓一さんのご子息である笠潤平さんが「字幕版」をつくってくれました。笠さんのお話は日本国憲法の誕生をめぐる貴重なものです。戦後80年のいまこそ、しっかり受け継ぎたいと思います。2022年2月23日放送、2025年9月20日字幕版掲載。
●93歳のわたしと憲法〜笠啓一さんに聞く
今年7月の参議院選挙を前に、改憲論議が高まっています。日本国憲法とは何か。憲法はどのように生まれ社会を変えたのか。いま、改めて憲法について考えてみたい、そんな思いに駆られます。
今回ゲストの笠啓一さんは、1928年生まれ、現在93歳です。ブレヒト劇の批評をはじめ、戦後の文化・芸術運動で活動してきました。笠さんは、旧憲法下、敗戦直後の憲法停止状態、そして現憲法下、三つの時代を生きてきました。それぞれの時代に何を経験し何を感じたのか。敗戦直後の状態について笠さんは「あの晴れ晴れとした感覚、上からの権力の重さを感じないで生きるという、これまで味わったことのない自由の味、フランス革命に言う「自由、平等、友愛」に通じるかと思われる解放感…」と記しています。そんな希望の時代をへて新しい憲法の時代が始まりました。しかし、70年後のいま、改憲の危機が迫っています。笠さんの「いま考えていること」をお聞きします。
●ゲスト=笠啓一(演劇批評家)
笠さんは1928年広島県生まれ、93歳。戦後早い時期から新日本文学会(1945-2005)の芸術運動に参加、主に演劇の分野で批評活動を展開した。著書に『歌が生まれる』、編訳書に『戯曲ガリレオ』がある。
●パーソナリティー=しまひでひろ/ささきゆみ
●技術=まつばらあきら
●配信スタジオ ビデオプレス
→笠啓一「憲法・戦争・沖縄」は こちら
●報告と感想: 日本人は「平和憲法」を空気のように受け入れた〜笠啓一さん語る
2月23日の「あるくラジオ」のテーマは「93歳のわたしと憲法」でゲストは笠啓一(りゅうけいいち)さんだった。戦争が終わったときが17歳。義兄はフィリピン沖で潜水艦の中で水没死したという。笠さんは「自分もお国のために死ぬのがあたりまえ」と本気で思う軍国少年だった。1945年の敗戦、そして新憲法の公布。パーソナリティがこう尋ねた。「憲法は押しつけという人がいますが、どうだったのですか?」。ゆっくり言葉を紡ぎ出す笠さん。「とんでもない。私たちは空気のように受け入れた。こんなひどい戦争がなぜ起きたのか。日本でもアジアでもひどいことをした。二度としてはだめだ。それが全国民のいつわざる気持ちで、憲法は日本人の体の中にすっぽり入っていたのです」「ダグラス・ラミス氏が書いているが、平和憲法がうまれたのはあの数年の時期しかなかった。国のタガがはずれ民の力が吹き出していた。とてもラッキーだった。アメリカと日本政府はすぐに再軍備をしようとしたが、民がそれを許さなかった」。そうだったんだ、聞いていて私の胸にストンと落ちた。
しかし戦後77年を経ていまや日本国憲法は風前のともしび。その後日本人は経済成長で浮かれてしまったのだろうか? 私も質問させてもらった。「なぜこうなってしまったと思いますか? メディア・教育・労働組合の弱化などが原因ですか? どうしたらいいですか?」。笠さんはこう答えた。「すべてその通りです。でも一番は私たちが市民社会をつくっていないこと。国家の横暴をとめる私たち主権者の意識が弱いことです。ガンジーは『主権者の尊厳』と言っていて、マルクスは奴隷制は『私たちは奴隷でない』と言った瞬間に終わると言っています。私たちが主権者だといえば、国を支配するかれらはびびります。戦争直後、自然発生的に読書会やサークルがつくられました。一人ひとりが本を読み、勉強し、討論しました。そんな小さなサークルから大きなサークルが生まれてくると思います」。
あっというまの1時間でたくさんのことが教えられた。市民社会とは自覚した主権者のネットワークなのか。私の体のなかにわき上がるものを感じた。その後、ラジオを聞いた人たちからも熱い反応が次々に届いている。ウクライナ危機で世界が戦争に向かっている今こそ、93歳・笠啓一さんの話を多くの人に聞いてほしいと思う。(松原明/「あるくラジオ」技術担当)
<「あるくラジオ」で笠さんが紹介した本>
①『ガンジーの危険な平和憲法案』(ダグラス・ラミス、集英社新書、2009年刊、680円)
②『〔増補〕憲法は政府に対する命令である』(ダグラス・ラミス、平凡社ライブラリー、2013年刊、1000円)
③『経済学批判要綱』(カール・マルクス、高木幸二郎監訳、5分冊、大月書店、古本で入手可能です)